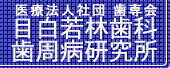一般的な入れ歯の治療例
入れ歯治療を成功に導くための条件は、
- 欠損部位
- 残存歯(天然歯)の部位と骨量
- 上下の噛み合わせの関係
- 患者さんが入れ歯を受け入れるための認識
など多くの情報を詳細に調べ、それを分析し、そして各々の症例に対して最適な入れ歯の設計を考案することです。
入れ歯治療の最大の指標は、入れ歯を入れて良かったと思ってもらえることでしょう。この指標を達成するためには、違和感がない、噛んでも痛くない、口の中にすんなり収まっている、即ち決して手放せない、生きた臓器のようだ、だから入れて良かった、に尽きるでしょう。
そこでこの指標を目指して色々な種類の入れ歯治療使用例を提示します。
症例 B1 下顎臼歯部片側欠損症例
噛む力で入れ歯全体が全く動かないことが必須条件となります。そのために欠損部の反対側に入れ歯の固定源を設計します。それは物を噛んでも沈まない、横ぶれしない、そして粘着する物を噛んでも浮き上がらないことを目的とします。

治療前(下顎) |
 |

治療後(下顎) |
入れ歯が動くと歯をゆすぶったり、とくに沈んだり、横ぶれすると欠損部(歯槽堤)が吸収し入れ歯が不適合となります。さらに欠損部と入れ歯の間に食べ物が入るようになり、食べずらくなったりします。
最適な入れ歯とは、欠損部と入れ歯が密着していることであり、ひいては入れ歯の長期的な機能につながることになります。 |
|

部分入れ歯 |
症例 B2 下顎臼歯部両側欠損症例
下顎臼歯部両側欠損の症例に対する入れ歯治療の要点は、両側欠損のため噛む力により入れ歯の後方が沈む可能性があります。
入れ歯の沈む原因は大きく分けて3つあります。
- 入れ歯が浮き上がることによって、その反動で沈むという現象です。それを防ぐために天然歯の前歯の舌の側(裏側)に→印のような細工を施し、浮き上がりを防止します。
- 物を噛んだ時の沈みは、欠損部と入れ歯の接する面積を可及的に大きくすることで、沈みを防ぎます。勿論、入れ歯が欠損部に限りなく密着していることが大切です。
- 噛んだ時入れ歯が強く当たると(高い)入れ歯が沈みますので、噛み合わせの調和が必要となります。
症例 B3 下顎臼歯部両側、前歯部欠損症例
臼歯部と前歯部欠損の設計の要点は、残存歯の数が少ないため残存歯と入れ歯を一体化することです。そのためには、出来る限り多くの残存歯と入れ歯を固定させるための細工(→印)が必要となります。
症例 B4 上顎臼歯部片側欠損症例
この症例は、1.下顎臼歯部片側欠損症例の治療使用例と全く同じ考え方によって設計しましたので参考にして下さい。
下顎の入れ歯の設計との違いは、下顎は常々舌が関与しているが上顎は発音に関わっているわけです。このような関わりに十分注意しながら入れ歯の有効性を考慮して設計します。上顎の入れ歯はうわ顎を効果的に使えるという利点があります。この症例は片側欠損ですから反対側に固定源を求めた設計です。
症例 B5 上顎臼歯部両側欠損症例
この症例は、残存歯8本が歯周病により中度の骨吸収が認められます。それ故、噛む力により、入れ歯の沈み、横ぶれ、浮き上がりを出来る限り防ぐ目的で上あご全体を使う設計をしました。

治療前 |
 |

治療後 |
この症例は、左右の臼歯5本を抜歯し、その日に前もって作成しておいた仮の入れ歯を入れました。その目的は、噛む機能や審美性の維持、即ち、入れ歯で上あごを覆うことが可能かどうかの判断をしたかったためです。
結果的に仮歯で違和感なく受け入れていただいたため最終的な入れ歯も全く同じ設計にすることが出来ました。患者さんはご自身の臓器にする惜しまぬ努力をされたと思いますが、現在、楽しい食生活を営んでいる様子がうかがえます。 |
|

治療後 |
症例 B6 上顎臼歯部両側前歯部欠損症例
この症例は、残存天然歯と入れ歯を一体化させるための設計をしました。
| 入れ歯の患者学 目白若林歯科歯周病研究所 03-3954-6681 |
|